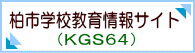文字
背景
行間
教育研究所からのお知らせ
初任者研修(第11回)
令和5年11月8日(水)初任者研修(第11回)を開催しました。
講義・演習:『児童生徒理解⑥子供の強みをいかす授業づくり~特別支援教育の視点から~』
児童生徒課
講義・演習:『学級経営⑤学級経営の改善』
教育研究所
講義・演習:『学習指導⑦子供の姿から考える授業改善』
教育研究所
1つ目の講義では,特別支援教育に関する支援のポイントやつまずきの背景を学びました。
2つ目の講義では,学級経営の改善に向けて,教育観について話し合いながら考えを深めていきました。
3つ目の講義では,主体的・対話的で深い学びについて振り返り,授業改善に向けた話し合いを行いました。
受講者からは,「惹きつけるための演出や,視覚的な支援も行い,スタートラインを揃えた授業を展開していきたいと思います。」「日々学び続けることで知識を身につけ,視点の転換を意識して児童と接することを大切にしていきたいと思いました。」「振り返りをすることで,学んだことを自覚し,次の学びにも繋がるとても意義のあることだと学びました。」等の声がありました。
初任者研修(第10回)
令和5年10月4日(水)初任者研修(第10回)を開催しました。
講義・演習:『健康教育の推進』
学校教育課
講義・演習:『食育の推進』
学校給食課
講義・演習:『児童生徒理解④~子どもの人権と学びの保障~』
児童生徒課
講義・演習:『児童生徒理解⑤~教育相談の基本~』
スクールカウンセラースーパーバイザー 髙井 千鶴
保健教育の在り方や,給食時間の実践的な指導例について学びました。
また,様々なケースを用いて,児童生徒の権利侵害から見る人権課題や,子どもへの関わり方について演習を行いました。
受講者からは,「小学校のうちから給食の時間や栄養士と協力して食の大切さを伝えていきたいです。」「こども食堂や教育支援センター,SSWやSCなどの外部機関を活用していきたい。」「困っている生徒の心に寄り添い安心感を与えることを心掛けたい。」等の声がありました。
初任者研修(第9回)
令和5年8月28日(月)初任者研修(第9回)を開催しました。
講義・演習:『チーム学校を支える協力体制づくり~コミュニティ・スクールの在り方を通して~』
学校教育課
講義・演習:『学級経営④学級経営の評価』
教育研究所
講義・演習:『児童生徒理解③保護者との関係づくり』
麗澤大学 教職センター 客員教授 鍵山 智子
講義・演習:『教育資源の利活用~学校図書館を活用した授業を通して~』
指導課
地域と学校の効果的な連携・協働体制の構築に関することや,保護者との関わり方,学校図書館の効果的な活用方法について学びました。
また,1学期の成果と課題を整理し,2学期以降の実践への見通しを持ちました。

受講者からは,「地域を積極的に知っていくことを大切にしたいと思いました。」「構成的グループエンカウンターのワークは,教師が意図を持って行うことによって,子どもたちに伝えたいことを伝えられるいい機会になると感じた。」「保護者との信頼関係を築くために大切なことを学びました。」「調べ学習の際,ICTと本を分けて考えるのではなく,その時にあった調べ方で情報を収集できるようにしたい。」等の声がありました。
中堅教諭等資質向上研修Ⅰ
令和5年8月25日(金)中堅教諭等資質向上研修Ⅰを開催しました。
講義・演習:『学校の力を高めるミドルへの期待1』
千葉大学 名誉教授 天笠 茂
講義・演習:『学校の力を高めるミドルへの期待2』
千葉大学 名誉教授 天笠 茂
講義・演習:『教育実践記録の中間報告』
教育研究所
ミドルリーダーとしてのカリキュラム・マネジメントの在り方や側面について学びました。

受講者からは,「他校の話を聞くことで教育課程を編成し直すきっかけになるので意見交換が出来て良かったです。」「評価方法について,自分の考えになかった新たな視点での評価方法を得ることができました。」等の声がありました。
管理職研修(2年目校長,新任校長,新任教頭,新任教務主任)
令和5年8月23日(水),24日(木)
管理職研修(新任校長,2年目校長,新任教頭,新任教務主任)を開催しました。
【2年目校長研修】
発表・協議:『共有ビジョンを具現化する方策』
教育研究所
講義・演習:『ビジョンの協働的な構築と組織体制の円滑化』
学校経営コンサルタント 木岡 一明
【新任校長研修】
発表・協議:『アクションリサーチから捉える成果と課題』
教育研究所
講義・演習:『具体的手立てを評価・診断する思考と方策』
学校経営コンサルタント 木岡 一明
【新任教頭研修】
発表・協議:『アクションリサーチを活用した実践の成果と課題』
教育研究所
講義・演習:『具体的手立てを評価・診断する思考と方策』
学校経営コンサルタント 木岡 一明
【新任教務主任研修】
発表・協議:『教育課程の意義と編成手順』
教育研究所
講義・協議:『カリキュラム・マネジメントの意義と教務主任の役割』
教育研究所
元名城大学教授の木岡一明先生を講師にお招きし,講義及び協議を行いました。
受講者からは,「校長として,自校の実態に合った学校教育目標や重点目標を作るにあたり,どのような方法で,どのような視点で進めていくか参考となる考えを聞くことができました。」「他校の校長先生方の実践や取り組みは,自身の振り返りに役立ちます。」「目標申告やビジョン展開シートに立ち返りながら日々の業務に取り組んでいきたいと思います。」「カリキュラムマネジメントを『見える化』することで,地域や保護者の信頼に繋がる重要性を知ることができました。」等の声がありました。