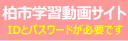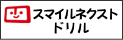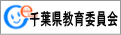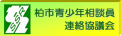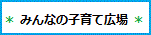|
||||||
文字
背景
行間
テガニっき 令和7年度
5年生 落花生の活動記録
5年生が総合の学習として、落花生の栽培・収穫・選別・販売にむけて活動しています。
今までの記事をまとめました。
<木村ピーナッツのInstagram>
★NEW★
https://www.instagram.com/pineki_kimura/
<子どもたちからの活動報告>
<活動計画>
<種まき>
<観察>
<収穫準備>
<販売準備>
★NEW★
〈収穫・選別〉★NEW★
〈人とのつながり〉★NEW★
5年生「落花生収穫・選別しました!!」
5年生は、2日間かけて落花生の収穫と選別を行いした。
<収穫>
5年生は、落花生を抜いてもぎ取りをしました。
上手に抜いたり、落花生の大きさを見ながらもぎ取りをしています。
たくさんの落花生が実っていて、みんな笑顔です。
<選別>
保護者と協力して、落花生の選別を行いました。
形や大きさ、音が鳴るかと一粒一粒確認しながら進めました。
たくさんの落花生を販売することができそうです。
2日間とも、会の進行も行いました。
地域の方との交流も忘れません。
10月4日土曜日10時から道の駅しょうなん
ツバサで落花生販売を行います。
たくさんの方に買いにきていただけると嬉しいです。お待ちしています。
5年生「落花生販売にむけて」
国語の学習で、落花生の販売場所を決めるためにディベートで話し合い活動をしています。
今回は、自分の立場を明確にし根拠となるデータや具体例を想像しやすい資料などを示しながら話すことを確認し
情報収集をしました。
手賀東のホームページやGoogleマップで場所の確認をして、資料や原稿を作りました。
第2回のディベートにむけて、準備をしています。
販売場所が決まりましたら、ホームページでもお知らせします。
1年生 算数「わかりやすくせいりしよう」
算数の「わかりやすくせいりしよう」で、問題文に〈つりゲーム〉という言葉が出てきてわくわくしている子どもたち。
学習では実際にゲームをしないのですが、自分たちで制作してやることに。
クリップをつければいいんだよ
磁石でくっつけよう
と意見を出し合いあっという間に完成しました。
簡単すぎないようにひもの長さを調節したり,魚を増やしたり工夫もがんばりました。
釣った後にはちゃんとダブレットを使って,数を整理しました。
5年生 落花生~子どもたちからの活動報告~
子どもたちが、落花生の活動についてまとめました。