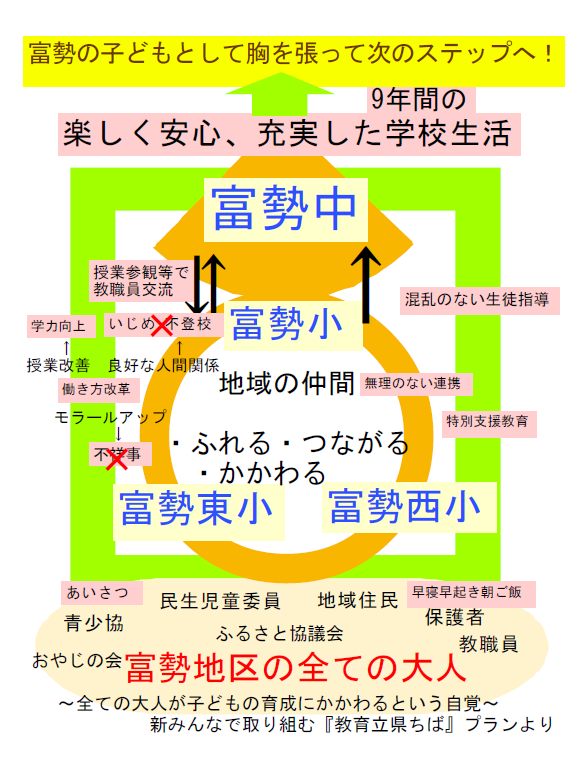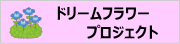文字
背景
行間
最近の出来事 令和7年度
4年生 総合的な学習「富勢の安全マップ」
4年生の総合的な学習の時間に、高野台公園で実施されている地域の夏祭りのことについてインタビューを受けていただくために、高野台町会の阿部様にご来校いただきました。
また、富勢小学区や柏市の交通安全に関するインタビューを受けていただくために、富勢駐在所の警察官後藤様にご来校いただきました。

夏祭りを継続するために、いろいろな工夫をしていること、人手不足でも地域のためにがんばっていることなど、インタビューで聞くことができました。

富勢学区で交通事故が多いのは農道だと意外な事実がわかったり、警察が様々な工夫をして事故防止に努力していることがわかったり、地域の人たちに何を発信していくかが、見えてきたようです。
お話の部屋ウィーク
昼休みにボランティアの「お話の部屋」の皆さんが、お話の部屋ウィークを開いてくださっています。今日は初日。面白いお話がテーマで、二つの読み聞かせがありました。

今日のスーパーゲストは教頭先生でしたが、お休みだったので校長先生が関西弁で読み聞かせてくれました。次回は教頭先生のお話をききましょうね。
県立柏高校天体観測会
11月15日の土曜日の夕方から、県立柏高校で天体観測会が開かれました。富勢小学校からも多くの親子で参加して、天文についての色々なお話を聞いたり、高校生の手作りプラネタリウムで星の話を聞いたり、屋上の天体望遠鏡で土星やその他の星を見たり、楽しい時間を過ごしました。

理数科の関谷先生は。JAXA出身で天体のお話はほんとうにおもしろい、すーっと引き込まれてしまいました。夏休みの理科教室や調べる学習教室にも、関谷先生と天文部をはじめとする生徒さんたちが来てくれていましたが、まさに学びの面白さを知っているから、子供へのサポートも楽しかったですね。

手作りの機械でのプラネタリウムは、ここまでできるかという逸品。大きなドームがあるので、学校でもやっていただきたいですね。

屋上での天体観測には、4台の天体望遠鏡に列をして秋の夜空を楽しみました。
5年生 日立イノベータープログラム中間発表
5年生は「理想の学校」に向けての探求的な学びを富勢西小学校と一緒に展開しています。今日はその中間発表会でした。

それぞれのグループごとに、自分たちで調べたり、アンケートをした結果などを基にした発表をしました。

発表後には、日立の社員の方々から、さらに自分たちの考えが伝わるようにするために、何が足りないのか、どういう構成で伝えるとよいか、次回の最終発表に向けて、優しくも厳しいご指摘をいただきました。
さあ、ここからが正念場です。
しいすまの子どもたちは4校交流をしました
「しいすま」の子どもたちは、朝から歩いて富勢中学校へ行きました。富勢4校の交流会です。それぞれの学校がリーダーになって、みんなで楽しくゲームなどをしました。富勢小学校はトップバッターを担当して、「オセロひっくりかえしゲーム」4校のみんなは、白と黒の板を返しながら楽しく遊びました。

富勢中学校は、「もうじゅうがりにいこうよ」です。文字の数に合わせてグループを組んで、他の学校の人たちともグループになって遊びました。


たくさんの友達と交流すると楽しいですね。
画像はあくまでも個人的に楽しまれる範囲で取扱われるようお願いいたします。画像等の情報は,他の情報と結びついて個人を特定させる性質があることから,情報悪用の危険が伴います。公開範囲が広ければ広いほど悪用されるリスクが高まります。公開範囲を限定していても,そのつながりを超えて漏れていく可能性があります。
一般的なマナーとして,SNS,動画サイト等への学校行事等の画像をアップする行為については,慎重さが求められます。
子どもを不審者被害や犯罪から守る観点からも御理解御協力の程,よろしくお願いいたします。
〒277-0825
千葉県柏市布施925-1
TEL:04-7133-2077
FAX:04-7134-5530
このホームページにおける文章、写真の著作権は柏市立富勢小学校にあります。無断転載は固くお断りします。