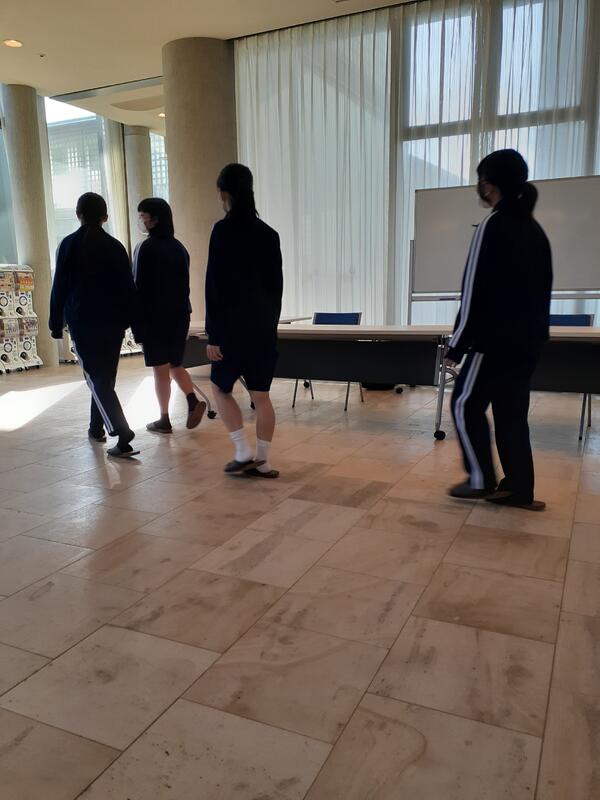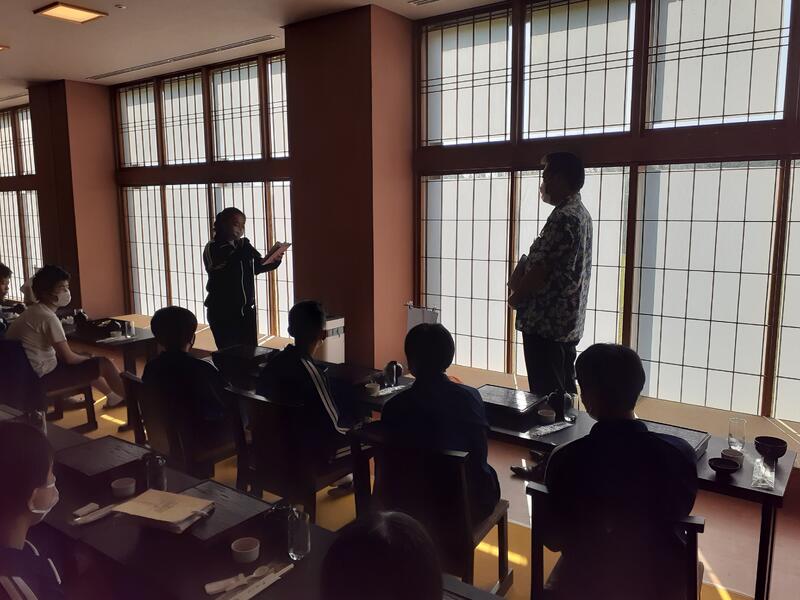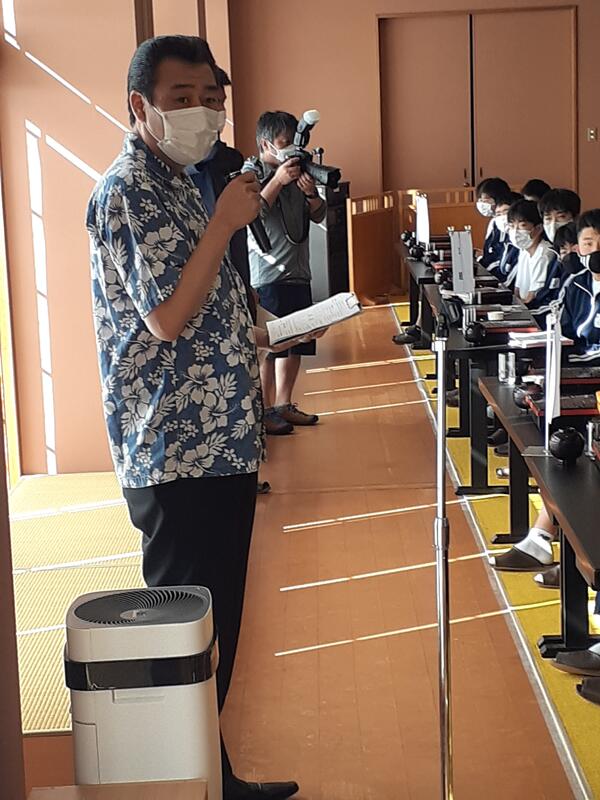創立78周年目 学び成長し続ける富勢中
文字
背景
行間
2022年6月の記事一覧
6月3日(金)雷雲の接近
〇天気予報通りに、午後から黒い雲が出て、埼玉方面からあっと言う間に、大きな雷雲が接近してきました。ちょうど帰りの会終了時刻が雨のピークになりましたので、生徒全員を下校せずに屋内で待機させています。竜巻やひょうの被害がないことを願います。
雨は止みませんが、大きな雷雲は通り過ぎましたので、生徒を下校させました。今後も地域的な豪雨や線状降水帯などの大雨が近づいた時の判断は難しいですが、情報を収集・整理していくしかありません。
須藤昌英
6月3日(金)最近の脳科学からわかること
〇先日紹介した、横浜創英中学・高等学校の工藤校長との共著で「自律するこの育て方」を執筆した応用神経科学者の青砥瑞人氏の見解も注目すべき点があります。長文ですが、引用させもらいます。
⇒ 考えたり記憶したりすることが人の成長や学びに大きなベクトルをもたらすこと、「学び」と「ウェルビーイング(しあわせ)」こそが教育の究極のゴールではないか。すなわち「率先して自分を成長させられる脳」かつ「率先して幸せな状態をつくることができる脳」を育てることが大切で、次の3点がそのためのポイント。
*脳の大原則①使わなければ失くすだけ
・普段から使っているネットワークはその状態を維持することができるが、使っていないネットワークは、休眠状態になるわけではなく、回路自体を切ってしまう。その理由は、脳の質量は体重の2%しかないのにもかかわらず、体内で使われるエネルギー(グルコース)は約25%を脳が占める
*脳の大原則② 人の意識は有限である
・人の脳のワーキングメモリーには限りがあり、同時にいくつもの作業はできない。このとき「どの情報を処理するか」を決定づけるのが、いわゆる「意識」や「注意」。脳の作業台(ワーキングメモリー)が雑多な情報やストレス、心配事などで散らかった状態のままでは、人は深い思考も高い集中力も発揮できない
*脳の大原則③ 人は本来ネガティブ思考が作動しやすい
・ネガティビティーバイアス(自己否定)に陥りやすい。その理由の一つは、脳の前頭前皮質には「エラー検知機能」があり、誤字脱字や計算ミス、他人の欠点や弱点を見抜く機能を備えている。また前帯状皮質には「自分のエラー検知機能」もあり、これは自分の欠点や弱点、自分の中の異変に注意を向けさせ、生存確率をあげようとする先天的な機能。もう一つの理由は、「人間の記憶の引き出し方」で、ポジティブよりもネガティブな記憶を強く思い出してしまう傾向がある。「人間は感情の生き物」でいかに理性的に考えようとしても難しい。子どもたちは褒められることよりもダメ出しされることに対して圧倒的に敏感。「子どもにダメ出ししたら、その分褒めればいい」という話ではない ⇒
〇特に私は、3つ目の「ネガティブな記憶を強く思い出してしまう」が大変気になりました。生徒に指導をする場面はたくさんありますが、それを「ダメ出し」と捉えさせるのではなく、「ここを直すともっと成長できるよ」というメッセージと受け止めてくれるようにしないと、本人のためを思っての指導が逆効果になってしまうなと感じました。
須藤昌英
(昨日の2学年林間学校より)
6月2日の振り返り
校長室に戻り、引率職員で反省会をしました。何より全員が無事で帰ってきたこと、優しい気持ちの生徒が多いこと、自立しようと努力する姿が見られたことなど・・、職員も生徒の成長を実感していました。
明日からの学校生活にいかしていきます。
須藤昌英
6月2日(木) 2学年林間学校第3日

バスが学校前に停車している間に、トランクから荷物を素早くおろし、そのまま下校です。生徒の皆さんお疲れ様でした。さようなら。
6月2日(木) 2学年林間学校第3日
岩井海岸を予定通り出発。幕張でトイレ休憩して、あとは学校に帰ります。
幕張サービスエリアを予定よりはやく出発します。学校にも予定よりはやく三時半には到着しそうです。ここまで生徒たちは、3日間を通して時間を意識して行動してくれました。素晴らしいと感心しきりの3日間でした。ご家庭でも誉めてあげて下さい。学校前でバスから降りたらそのまま下校します。明日は2学年のみ、10時15分登校になります。疲れていますので、ご家庭で様子を見て下さい。
6月2日(木) 2学年林間学校第3日
獲れた魚の説明がありました。メジナ 黒鯛 サクラ鯛 カンパチやブリの子ども ホウボウ シロギス です。すべてこれから、あら汁にしてくれます。
クラスごとに民宿に移動し、昼食です。
6月2日(木) 2学年林間学校第3日
岩井海岸に到着。サンダルで浜に向かいます。サンダルを忘れた生徒は、裸足で参加です。江戸時代からの漁法を体験します。
岩井海岸は浜風が気持ち良く、暑さは感じません。上空では、トンビが魚を狙っています。女子は「キャーキャー」と大騒ぎでした。
6月2日(木) 2学年林間学校第3日
最終日のメインイベントである地引き網体験に向けて、再び外房の九十九里から内房の岩井海岸に向けて、出発です。
トイレ休憩
6月2日(木) 2学年林間学校第3日
生徒たちが朝食会場に集まる時や食べている最中に様子を観察し、具合の悪い生徒がいないかをチチェックします。
2泊お世話になったホテルの方に、代表の吉岡さんからお礼の言葉を差し上げました。ホテルの方からは、「今日の地引き網体験を頑張ってください。また機会がありましたら、ご家族と一緒にお越しください」と挨拶がありました。聞いている生徒たちも礼儀正しく、私も教員三十六年目ですが、これだけ自慢できるような生徒たちは初めてです。
6月2日(木) 2学年林間学校第3日
今朝は太平洋からのぼる日の出が見えました。今日も汗ばむような気温らしいので、健康観察をしっかり行います。