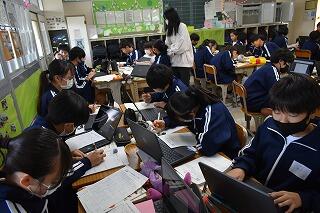創立79年目 学び成長し続ける富勢中
文字
背景
行間
R7_富勢中日記
R7_富勢中日記
10月30日 授業の様子
理科の授業は,実験を行っています。班で協力しながら進めていて楽しそうです。
体育はバレーボールやソフトボールなど,家庭科では栄養について調べていました。
調べてことや学んだことをグループで発表して,質問をうけるとより学びが深まります。
真剣に授業に臨んでいました。
10月29日 歌声交換会
来週の合唱コンクールに向けて,各クラス熱のこもった練習をしています。
他のクラスと歌声を披露し合う交換会も行われており,良い点やもっと良くなる点を確認しています。
上級生はやはりすごいなと感じ,下級生の合唱で上級生は気合が入ります。
お互いに刺激となり,さらに気持ちが高まります。
本番にどれほどの合唱ができるようになるかとても楽しみです。
10月28日 花の水やり
花鉢ボランティアの活動で,プール脇のスペースでビオラを育てています。
最近は雨が続いていましたが,今日は秋晴れ。
朝少し早めに登校して,花の水やりをしてくれています。
10月27日 教育実習終了
10月6日から始まった教育実習が,期間は2週間や3週間などそれぞれ違いましたが,本日ですべて終了します。
授業や休み時間,行事などの活動を通して,様々なことを学び,子どもたちと共に成長できた教育実習になったと思います。
近い将来,教壇に立って,活躍してくれることを期待します。
10月24日 2年生リハーサル
2年生は合唱コンクールのリハーサルを行いました。
動きの確認を中心に,各学級が短く発表しました。
自信を持って歌えるようラストスパート頑張りましょう。