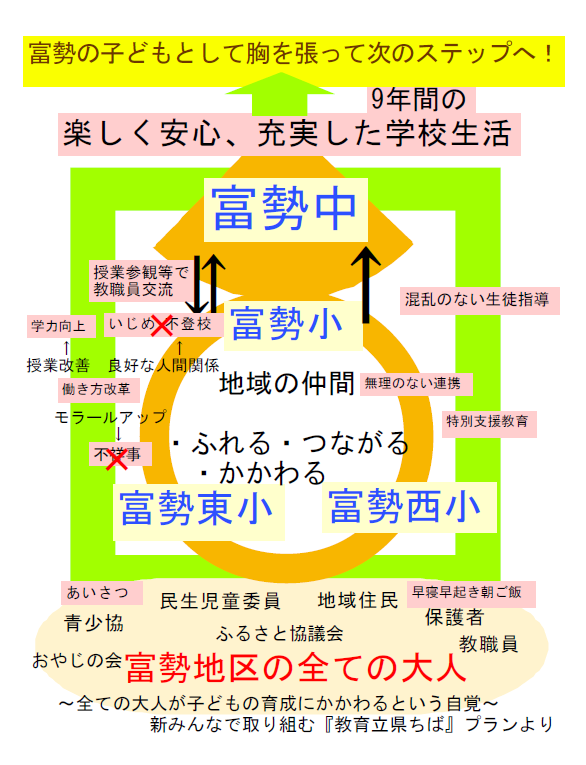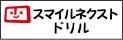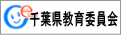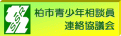文字
背景
行間
校長ブログ(令和7年度)
2月の学校便りより 児童会役員選挙に寄せて
2月8日(日)に衆議院議員総選挙が行われることになりました。総選挙に向けて、各党の選挙活動が始まっています。まさか同じタイミングになるとは思いませんでしたが、本校でも児童会役員選挙に向け、今週から選挙活動が始まりました。本校では、平成30年1月29日に児童会役員選挙の立会演説会があったようですが、その後はコロナ禍で児童会そのものがなくなり、選挙も行われていませんでした。そのため、児童会役員選挙は、7年ぶりになります。子ども達はもちろん初めてです。
本校は、「子どもが主語の学校」を目指しています。子ども達自身が自分たちの学校を、自分たちの生活をよりよくするためにはどうしたらよいかを考え、児童会を中心に自治を進めてほしいと思っています。学校は小さな社会。子ども達と共によりよい社会を築く新たな一歩を進めます。
3学期が始まりました!
新年明けましておめでとうございます。2026年は午(うま)年(どし)、それも「丙午(ひのえうま)」という60年に一度巡ってくる特別な年になりました。丙午の年は、「勢いとエネルギーに満ちて、活動的になる」と言われているそうです。本校もこれまでの挑戦や取り組みが、より情熱を帯び、ゴールに向かって駆け抜ける馬のごとく、力強く進んでいけたらと思っております。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、3学期の始業式は、旭町会お囃子保存会による「獅子舞」披露から幕を開けました。冬休みは、日本の伝統文化に触れる機会が普段より多かったと思いますが、どこの地域も文化の継承は大きな課題となっています。それは富勢地域も例外ではなく、「布施囃」の後継者がいないとのことでした。学校は子供たちに伝統文化を伝える大事な役割も担っています。自分の住んでいる地域や日本の伝統について関心を持ち、人から人へと引き継がれる文化の担い手になってもらえたらと思います。
3学期も地域学習を中心に、地域と共にある学校を目指してまいります。
2学期を終えて・・・
12月23日は2学期の最終日でした。
各学年の代表児童が2学期頑張ったことを発表してくれました。
音楽発表会に弁天マラソン大会、算数の自由進度学習に個人探究、全校遠足や委員会活動など、それぞれ色々な場面で頑張ったことを話してくれました。
6年生は、卒業文集に書いた6年間の思い出を発表してくれました。
どの子の作文からも、その子らしさやその子の努力、その子の感性や成長が感じられ、胸が熱くなりました。
子供は当たり前ですが一人一人違います。興味や能力、特性も違います。感じ方も様々です。だからこそ、学校には色々な場面が必要だし、その子が選択できる幅が必要だと思っています。
12月9日に行った弁天マラソン大会(持久走大会)は、子ども達が話し合い、初めて選択制という方法で行いました。私は子供たちが「走るのも苦手な人も楽しめる大会にしよう」とアイディアを出し合い、話し合った過程に大きな価値があったと思います。中心となった体育委員会はもちろん、委員会を支えた6年生や先生方、応援してくださった保護者の皆様に心から感謝したいと思います。
3学期は、児童会を発足させます。子どもたちが自分たちの学校をよりよくするため、みんなで協力し合える学校を共に創っていきたいと思います。
3学期もよろしくお願いいたします。
12月の学校便りより
11月は、修学旅行から始まり、全校遠足で終わるという「特別活動」の重点月間となりました。子ども達は、全校遠足に向けて、各学年や縦割りグループでそれぞれの役割を果たし、準備を進めてきました。全校遠足の行き先は、初めての国立科学博物館。高学年がリーダーシップを発揮し、みんなで協力しながら行動し、たくさんの発見や学びを得られたようです。改めて6年生の存在を頼もしく思いました。子ども達は行事を通して成長するとよく言われます。海外でも日本の「トッカツ」は高く評価され、広がりを見せています。私達はこれからも「子供主体の特別活動」を目指していきたいと思います。
修学旅行を終えて・・・
11月6日(木)、7日(金)に6年生と修学旅行へ行ってきました。
行き先は鎌倉と都内、電車での修学旅行です。
コロナ禍を経て本校では、都内と県内(成田・佐原・佐倉方面)を中心に旅行をしていましたが、バス代の高騰もあり、電車で行かれる場所を探して、今年度初めて鎌倉方面への旅行を実施することにしました。
まずは我孫子駅から北鎌倉駅へ。市内散策は、8時30分から14時まで自由行動。子ども達は事前に行きたい場所を申告し、グループを決めていきました。
班ごとに寺院や大仏を見学したり、小町通りで食べ歩きをしたり・・・。思い思いに旅行を楽しむ姿が見られ、外国の方へのインタビューも積極的に行っていました。普段の外国語の授業の成果も十分に発揮できたようです。
宿泊先は、浅草のホテル。夜は、スカイツリーから大都会の夜景を楽しみました。
2日目は、東京証券取引所と国会議事堂の見学。1日目は、歴史を学び、2日目は経済と政治を学ぶ。修学旅行としてはかなり充実した内容だったと思います。
電車での移動は、貸し切りバスと違い、引率する側としても常に緊張感が伴いますが、子供たちがマナー良く乗車し移動してくれたおかげで、予定通り進めることができました。
6年生のたくさんの笑顔と成長ぶりに触れられた修学旅行は、初めての試みも多くありましたが、本校の歴史に残る素晴らしい修学旅行だったと思います。
ご協力いただいた保護者の皆様、旅行先でお世話になった方々に心から感謝したいと思います。ありがとうございました。
また、何よりも主役の子供たちにも感謝したいです。2日間よく頑張りましたね。
新たな歴史を刻んでくれて、これからに続く第一歩を踏み出してくれて、本当に嬉しく思います。皆さんと過ごした思い出は、ずっと忘れません。本当にいい修学旅行でした。どうもありがとう。


11月の学校便りより
今年度から始まった委託での水泳学習が10月29日で終わりました。限られた回数でしたが、最適な環境の中で、専門的な指導を受け、子ども達はどんどん泳げるようになっていきました。一人一人の経験や泳力にはかなりの差があり、今回は4つのグループに分かれての指導でしたが、どの子もめいっぱい活動する姿が見られ、その子に合わせた指導がいかに大切であるかを実感することができました。
学校現場では今、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を目指す授業」が求められています。これは、誰一人取り残さず、すべての子の可能性を最大限に引き出すためのものです。水泳学習のように、他の授業でも私達はすべての子にとって最適な学びをこれからも追求していきたいと思います。
前期を終えて・・・
10月3日(金)に前期の通知表を配付します。
本校では4月から9月を前期、10月から3月を後期として評価をしています。
今年度は全校教科担当制に変わったため、それぞれの教科担当が3段階の評価をし、所見は担任がまとめるという形になりました。
また、4年生以上は、総合的な学習の時間に「フリースタイルプロジェクト」(個人探究)に取り組んだため、その内容を記録として記載しました。
初めての探究学習だったので、内容が十分でなかった子もいたかもしれませんが、通知表の記録を見ていると、それぞれの興味関心が分かり、個性が光り輝いているように見えました。自分の好きなこと、興味のあること、自分が疑問に思っていることを追求することは、自分を知り、自分の良さを伸ばすことにつながると思います。また、お互いの発表を通じて、友達の新たな一面に気づき、相手を知ることにもつながったのではないかと感じました。
後期の総合的な学習の時間は、学年ごとに「地域の担い手を育む」を主題に取り組みます。今度は、地域の方々や富勢地区の子供たちと交流しながら、地域の良さや現状を知り、課題を解決する力をつけていってほしいと思います。
また、前期は、記録的な猛暑で、外遊びや運動の機会が十分に取れませんでした。後期は、体力向上にも積極的に取り組んで参りたいと思います。
10月の学校便りより
9月19日は、お陰様で素晴らしい会場で思い出に残る音楽発表会を行うことができました。ご協力いただき、本当にありがとうございました。子供たちは、いつもと違った雰囲気にかなり緊張した様子でしたが、練習の成果を見事に発揮してくれました。子供たちの合唱や合奏の音色、一生懸命な姿に私も感動しました。みんなで何かを成し遂げた経験が、子供たちの心の豊かさや成長につながってくれているといいなと思います。これからもたくさんの経験を積ませてあげたいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
来週から2学期が始まります!
今年の夏は「災害級の猛暑」という言葉が聞かれる程、記録的な暑さが続きました。外で遊べる時間が限られ、厳しい夏休みだったかもしれませんが、お陰様で本校では大きな事故もなく、2学期が迎えられそうです。ありがとうございました。子ども達に会えるのが楽しみです。
さて、この夏、私は宮城県石巻市震災遺構大川小学校へ行ってきました。東日本大震災の津波によって児童74名、教職員10名が犠牲となった学校です。「止まった刻」という書籍を以前に読み、胸に迫るものがあったため、もう一度読み直してから行きました。敷地に一歩入ると、校庭から子供たちの声が聞こえてきそうで涙があふれ、そして「なぜ」という問いが何度も繰り返し頭に浮かびました。子ども達の命を守ることは学校の第一条件。しっかりと防災・安全対策を行い、命を守る教育をしていかなくてはと改めて強く感じました。本年度も、9月1日にシミュレーション引き渡し訓練を行います。2学期も様々な教育活動にご協力をよろしくお願いいたします。
7月を迎えて
【7月の学校便りより】
色とりどりの紫陽花が雨に濡れてきれいに咲いています。紫陽花の花の色は、土壌の酸性度によって変化するそうです。同じ種類でも環境によって色が変わる紫陽花を見ると、人間も同じだなあと感じてしまいます。元々持っているその子の特性や可能性も、環境によって変化すると考えてしまうからです。環境の影響は、大人よりも子どもの方が大きいのではないでしょうか。大人は自分の意志で環境を変えることができても、子どもはなかなか難しい・・・そう考えると、子どもたちの育つ土壌をより良くし、その子の持っている可能性を十分に伸ばせるような環境をつくっていくことは大人の使命だと思います。
先日の授業参観で、「子どもの権利条約」についてみんなで学びました。子どもの権利を守り、子ども時代を豊かに安心して過ごせるよう、学校も家庭も一緒になって子どもたちを支えていきたい、改めてそう思いました。子どもたちには、今も未来も自分で幸せをつかめるようになってほしいと願っています。そのための教育活動をこれからも続けて参ります。
6月16日(月)~21日(土)までの間、異学年の自由進度学習に全校で取り組みました。これも、子供たちの可能性を伸ばす土壌づくりの一つです。
異学年で学習することの良さは、自己肯定感や自己有用感が育まれること、学習の予習や復習ができたり、学びあいがしやすくなったりすることにあると考えています。異学年が混ざり合うと、心理的な安心感が高まり、自然に「教えて」や「分からない」という言葉も出ます。私は、そうした環境の中で、子ども達が自分の持っている力を十分に発揮し、可能性を伸ばしてほしいと願っています。
自由進度学習も、全校で行うことで、教員同士がチームを組み、みんなで子ども達の支援をしました。「教える」から「学ぶ」への授業観の転換を図り、自立した学習者を育てることがねらいです。私達は、これからも、子ども達の主体的な学びの伴走者となり、子ども達一人一人が自分らしく、自分の色の花を咲かせられるように、また、学ぶことが楽しいという喜びを得られるように、豊かな土壌を作っていきたいと思っています。
校長ブログ(令和7年度)
2月の学校便りより 児童会役員選挙に寄せて
2月8日(日)に衆議院議員総選挙が行われることになりました。総選挙に向けて、各党の選挙活動が始まっています。まさか同じタイミングになるとは思いませんでしたが、本校でも児童会役員選挙に向け、今週から選挙活動が始まりました。本校では、平成30年1月29日に児童会役員選挙の立会演説会があったようですが、その後はコロナ禍で児童会そのものがなくなり、選挙も行われていませんでした。そのため、児童会役員選挙は、7年ぶりになります。子ども達はもちろん初めてです。
本校は、「子どもが主語の学校」を目指しています。子ども達自身が自分たちの学校を、自分たちの生活をよりよくするためにはどうしたらよいかを考え、児童会を中心に自治を進めてほしいと思っています。学校は小さな社会。子ども達と共によりよい社会を築く新たな一歩を進めます。
3学期が始まりました!
新年明けましておめでとうございます。2026年は午(うま)年(どし)、それも「丙午(ひのえうま)」という60年に一度巡ってくる特別な年になりました。丙午の年は、「勢いとエネルギーに満ちて、活動的になる」と言われているそうです。本校もこれまでの挑戦や取り組みが、より情熱を帯び、ゴールに向かって駆け抜ける馬のごとく、力強く進んでいけたらと思っております。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、3学期の始業式は、旭町会お囃子保存会による「獅子舞」披露から幕を開けました。冬休みは、日本の伝統文化に触れる機会が普段より多かったと思いますが、どこの地域も文化の継承は大きな課題となっています。それは富勢地域も例外ではなく、「布施囃」の後継者がいないとのことでした。学校は子供たちに伝統文化を伝える大事な役割も担っています。自分の住んでいる地域や日本の伝統について関心を持ち、人から人へと引き継がれる文化の担い手になってもらえたらと思います。
3学期も地域学習を中心に、地域と共にある学校を目指してまいります。
2学期を終えて・・・
12月23日は2学期の最終日でした。
各学年の代表児童が2学期頑張ったことを発表してくれました。
音楽発表会に弁天マラソン大会、算数の自由進度学習に個人探究、全校遠足や委員会活動など、それぞれ色々な場面で頑張ったことを話してくれました。
6年生は、卒業文集に書いた6年間の思い出を発表してくれました。
どの子の作文からも、その子らしさやその子の努力、その子の感性や成長が感じられ、胸が熱くなりました。
子供は当たり前ですが一人一人違います。興味や能力、特性も違います。感じ方も様々です。だからこそ、学校には色々な場面が必要だし、その子が選択できる幅が必要だと思っています。
12月9日に行った弁天マラソン大会(持久走大会)は、子ども達が話し合い、初めて選択制という方法で行いました。私は子供たちが「走るのも苦手な人も楽しめる大会にしよう」とアイディアを出し合い、話し合った過程に大きな価値があったと思います。中心となった体育委員会はもちろん、委員会を支えた6年生や先生方、応援してくださった保護者の皆様に心から感謝したいと思います。
3学期は、児童会を発足させます。子どもたちが自分たちの学校をよりよくするため、みんなで協力し合える学校を共に創っていきたいと思います。
3学期もよろしくお願いいたします。
12月の学校便りより
11月は、修学旅行から始まり、全校遠足で終わるという「特別活動」の重点月間となりました。子ども達は、全校遠足に向けて、各学年や縦割りグループでそれぞれの役割を果たし、準備を進めてきました。全校遠足の行き先は、初めての国立科学博物館。高学年がリーダーシップを発揮し、みんなで協力しながら行動し、たくさんの発見や学びを得られたようです。改めて6年生の存在を頼もしく思いました。子ども達は行事を通して成長するとよく言われます。海外でも日本の「トッカツ」は高く評価され、広がりを見せています。私達はこれからも「子供主体の特別活動」を目指していきたいと思います。
修学旅行を終えて・・・
11月6日(木)、7日(金)に6年生と修学旅行へ行ってきました。
行き先は鎌倉と都内、電車での修学旅行です。
コロナ禍を経て本校では、都内と県内(成田・佐原・佐倉方面)を中心に旅行をしていましたが、バス代の高騰もあり、電車で行かれる場所を探して、今年度初めて鎌倉方面への旅行を実施することにしました。
まずは我孫子駅から北鎌倉駅へ。市内散策は、8時30分から14時まで自由行動。子ども達は事前に行きたい場所を申告し、グループを決めていきました。
班ごとに寺院や大仏を見学したり、小町通りで食べ歩きをしたり・・・。思い思いに旅行を楽しむ姿が見られ、外国の方へのインタビューも積極的に行っていました。普段の外国語の授業の成果も十分に発揮できたようです。
宿泊先は、浅草のホテル。夜は、スカイツリーから大都会の夜景を楽しみました。
2日目は、東京証券取引所と国会議事堂の見学。1日目は、歴史を学び、2日目は経済と政治を学ぶ。修学旅行としてはかなり充実した内容だったと思います。
電車での移動は、貸し切りバスと違い、引率する側としても常に緊張感が伴いますが、子供たちがマナー良く乗車し移動してくれたおかげで、予定通り進めることができました。
6年生のたくさんの笑顔と成長ぶりに触れられた修学旅行は、初めての試みも多くありましたが、本校の歴史に残る素晴らしい修学旅行だったと思います。
ご協力いただいた保護者の皆様、旅行先でお世話になった方々に心から感謝したいと思います。ありがとうございました。
また、何よりも主役の子供たちにも感謝したいです。2日間よく頑張りましたね。
新たな歴史を刻んでくれて、これからに続く第一歩を踏み出してくれて、本当に嬉しく思います。皆さんと過ごした思い出は、ずっと忘れません。本当にいい修学旅行でした。どうもありがとう。


11月の学校便りより
今年度から始まった委託での水泳学習が10月29日で終わりました。限られた回数でしたが、最適な環境の中で、専門的な指導を受け、子ども達はどんどん泳げるようになっていきました。一人一人の経験や泳力にはかなりの差があり、今回は4つのグループに分かれての指導でしたが、どの子もめいっぱい活動する姿が見られ、その子に合わせた指導がいかに大切であるかを実感することができました。
学校現場では今、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を目指す授業」が求められています。これは、誰一人取り残さず、すべての子の可能性を最大限に引き出すためのものです。水泳学習のように、他の授業でも私達はすべての子にとって最適な学びをこれからも追求していきたいと思います。
前期を終えて・・・
10月3日(金)に前期の通知表を配付します。
本校では4月から9月を前期、10月から3月を後期として評価をしています。
今年度は全校教科担当制に変わったため、それぞれの教科担当が3段階の評価をし、所見は担任がまとめるという形になりました。
また、4年生以上は、総合的な学習の時間に「フリースタイルプロジェクト」(個人探究)に取り組んだため、その内容を記録として記載しました。
初めての探究学習だったので、内容が十分でなかった子もいたかもしれませんが、通知表の記録を見ていると、それぞれの興味関心が分かり、個性が光り輝いているように見えました。自分の好きなこと、興味のあること、自分が疑問に思っていることを追求することは、自分を知り、自分の良さを伸ばすことにつながると思います。また、お互いの発表を通じて、友達の新たな一面に気づき、相手を知ることにもつながったのではないかと感じました。
後期の総合的な学習の時間は、学年ごとに「地域の担い手を育む」を主題に取り組みます。今度は、地域の方々や富勢地区の子供たちと交流しながら、地域の良さや現状を知り、課題を解決する力をつけていってほしいと思います。
また、前期は、記録的な猛暑で、外遊びや運動の機会が十分に取れませんでした。後期は、体力向上にも積極的に取り組んで参りたいと思います。
10月の学校便りより
9月19日は、お陰様で素晴らしい会場で思い出に残る音楽発表会を行うことができました。ご協力いただき、本当にありがとうございました。子供たちは、いつもと違った雰囲気にかなり緊張した様子でしたが、練習の成果を見事に発揮してくれました。子供たちの合唱や合奏の音色、一生懸命な姿に私も感動しました。みんなで何かを成し遂げた経験が、子供たちの心の豊かさや成長につながってくれているといいなと思います。これからもたくさんの経験を積ませてあげたいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
来週から2学期が始まります!
今年の夏は「災害級の猛暑」という言葉が聞かれる程、記録的な暑さが続きました。外で遊べる時間が限られ、厳しい夏休みだったかもしれませんが、お陰様で本校では大きな事故もなく、2学期が迎えられそうです。ありがとうございました。子ども達に会えるのが楽しみです。
さて、この夏、私は宮城県石巻市震災遺構大川小学校へ行ってきました。東日本大震災の津波によって児童74名、教職員10名が犠牲となった学校です。「止まった刻」という書籍を以前に読み、胸に迫るものがあったため、もう一度読み直してから行きました。敷地に一歩入ると、校庭から子供たちの声が聞こえてきそうで涙があふれ、そして「なぜ」という問いが何度も繰り返し頭に浮かびました。子ども達の命を守ることは学校の第一条件。しっかりと防災・安全対策を行い、命を守る教育をしていかなくてはと改めて強く感じました。本年度も、9月1日にシミュレーション引き渡し訓練を行います。2学期も様々な教育活動にご協力をよろしくお願いいたします。
7月を迎えて
【7月の学校便りより】
色とりどりの紫陽花が雨に濡れてきれいに咲いています。紫陽花の花の色は、土壌の酸性度によって変化するそうです。同じ種類でも環境によって色が変わる紫陽花を見ると、人間も同じだなあと感じてしまいます。元々持っているその子の特性や可能性も、環境によって変化すると考えてしまうからです。環境の影響は、大人よりも子どもの方が大きいのではないでしょうか。大人は自分の意志で環境を変えることができても、子どもはなかなか難しい・・・そう考えると、子どもたちの育つ土壌をより良くし、その子の持っている可能性を十分に伸ばせるような環境をつくっていくことは大人の使命だと思います。
先日の授業参観で、「子どもの権利条約」についてみんなで学びました。子どもの権利を守り、子ども時代を豊かに安心して過ごせるよう、学校も家庭も一緒になって子どもたちを支えていきたい、改めてそう思いました。子どもたちには、今も未来も自分で幸せをつかめるようになってほしいと願っています。そのための教育活動をこれからも続けて参ります。
6月16日(月)~21日(土)までの間、異学年の自由進度学習に全校で取り組みました。これも、子供たちの可能性を伸ばす土壌づくりの一つです。
異学年で学習することの良さは、自己肯定感や自己有用感が育まれること、学習の予習や復習ができたり、学びあいがしやすくなったりすることにあると考えています。異学年が混ざり合うと、心理的な安心感が高まり、自然に「教えて」や「分からない」という言葉も出ます。私は、そうした環境の中で、子ども達が自分の持っている力を十分に発揮し、可能性を伸ばしてほしいと願っています。
自由進度学習も、全校で行うことで、教員同士がチームを組み、みんなで子ども達の支援をしました。「教える」から「学ぶ」への授業観の転換を図り、自立した学習者を育てることがねらいです。私達は、これからも、子ども達の主体的な学びの伴走者となり、子ども達一人一人が自分らしく、自分の色の花を咲かせられるように、また、学ぶことが楽しいという喜びを得られるように、豊かな土壌を作っていきたいと思っています。
校長ブログ(令和6年度)
令和6年度の修了式を終えて
つくしやタンポポ、オオイヌノフグリやヒメオドリコソウなど一斉に野の花が咲き始め、春の訪れを感じるこの頃です。寒い冬を乗り越えて、けなげに咲いた花々を見ると、どこか子どもたちの姿と重なります。
子どもたちは、今年1年間、本当によく頑張り、それぞれ成長することができました。
修了式の子どもたちの顔は、どこか誇らしく、一人一人の笑顔は色とりどりに咲いた花のようでした。
子どもたちは毎年私達に教えてくれます。
一日一日の積み重ねは小さくても、それが1年間続くと大きな成長につながるということを・・・。
お互いに学び合い、成長し合うのが学校です。成長し合えた喜びを称え合った修了式でした。
ここまで子どもたちの成長を支えてくださった、保護者の皆様、地域の皆様に心から感謝申し上げます。一年間、本当にありがとうございました。
そして、来年度も引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
卒業証書授与式を終えて・・・
3月14日(金)令和6年度卒業証書授与式をお陰様で無事に終えることができました。
今年の卒業生は、第46回生 18名。みんなやさしくて、下級生に慕われるいい子たちです。
一人一人壇上で夢を語り、卒業証書を受け取る姿は、堂々としていて、とても立派でした。
練習の始めの頃は、声が小さかったり、言葉がはっきり聞こえなかったりして心配しましたが、本番までにしっかり仕上げてくるところはさすがでした。合唱も同様です。力のある子どもたちだなあと改めて感じました。素晴らしい姿を最後に在校生に見せてくれた卒業生に、感謝の気持ちでいっぱいになりました。
また、在校生も卒業生に対する感謝とお祝いの気持ちをこめて、どの子も一生懸命呼びかけをしたり、合唱をしたりしていました。最後の全校合唱は、富勢東小の子どもたちの美しいハーモニーが響き合い、心から感動しました。
全校の卒業式にして良かったです。最高の卒業式になりました。
卒業生の皆さん、ご卒業、本当におめでとうございます。
また、保護者の皆様、お子様のご卒業、誠におめでとうございます。
皆様のご健康とご多幸、そして益々のご活躍を職員一同、心より祈念しております。
6年生を送る会を終えて・・・
2月21日金曜日、6年生を送る会がありました。送る会が終わると、いよいよ卒業だなと感じます。
急に寂しさもこみ上げてきました。今年の6年生は、みんな優しくて、下級生からも慕われ、頼りにされていました。だからなのでしょう。会場は、6年生への感謝や大好きという気持ちであふれていたように思います。本校のあたたかい空気は、ここまで引っ張ってきてくれた6年生の存在が大きかったんだなあと改めて感じました。6年生、本当にありがとう。
本校は、全校児童が101名、6年生は18人しかいません。少ない人数ですが、その分お互いの絆は深く、学年を超えた思い出も沢山あります。一番長く一緒にいた5年生が作ったスライドには、6年生一人一人との思い出や感謝が詰まっていて、見ていて胸が熱くなりました。3・4年生は、タイムマシンで1年生まで遡り、6年間の楽しかった思い出を蘇らせてくれました。ジャンボリーミッキーや林間学校のダンスを見ていると、当時の楽しさも伝わってくるようでした。気持ちがこもった歌も感動しました。1・2年生は、6年生の将来の夢をみんなに伝えてくれました。緊張した様子で演技をしたり、お話したり・・・。一生懸命表現する姿が微笑ましかったです。6年生も以前はこんなに小さかったんだなあと想像したりしました。成長した6年生の将来が益々楽しみになりました。元気な歌声も良かったです。
送る会は、教育課程でいうと、「特別活動」にあたります。特別活動は、「なすことによって学ぶ」というものです。教師が指導するのではなく、子どもが主体となって活動し、経験を通して学んでいくことが大切です。今回は、子どもたちが色々とアイディアを出し、送る会を成功させてくれました。全校合唱を聞きながら、みんなの力が合わさると凄いなあと感じました。子どもが主体であると、当然失敗することもあるでしょう。でも、それこそが学習の機会。人生に失敗はつきものなのですから。子どもたちには、沢山の失敗や経験を通して、これからも大きく、のびのびと、その子らしく成長していって欲しいなと思います。
もちろん、小学校を卒業した後も・・・。卒業式は3月14日、修了式は3月24日です。残り少ない日々を元気に、楽しく過ごしてほしいと思います。
学校の挑戦
3学期に入ってから、学校では、「まずはやってみよう!」の精神で、様々な取組を行っています。
一つ目は、全学年で自由進度学習を行うというものです。
「自由進度学習」とは、児童が学習計画を立てて学習を進める方法であり、自分のペースで自分に合ったやり方で学びを進めていくことができます。よく、「一人で学習を進めていると、分からないことがあってもそのままになってしまって、学習が遅れてしまうのではないか」、「遊んでしまうのではないか」、「孤立した学びになるのでは?」といった心配も聞くのですが、そういった不安は根底に「子どもは教えないと学べない」という考え方があるように思います。しかし、元々子どもは有能な学び手です。遊びながら、生活しながら、色々なことを覚え、できるようになってきたのではないかと思います。私達は、そのような子どもたちの力を信じ、学校教育目標である「自ら学ぶ子」を育てていこうというのが今回の試みです。
実は、5年生は、年間を通して、単元内自由進度学習に取り組んでいました。この度、それをまとめた担任の実践論文が柏市で表彰を受け、私達にとっても大きな自信になりました。
「令和の日本型学校教育」は、全ての子どもたちの可能性を引き出す、個別最適な学びと協働的な学びの実現を目指しています。これまでの一斉授業は「教える」ことが中心でしたが、これからは子どもが主体となって「学ぶ」ことを目指していこうというものです。一斉授業がなくなるわけではありませんが、子どもが主体となる学びはどんどん進めていきたいと考えています。
二つ目の取組は、異年齢での学びです。1月に1週間、3学年ずつの縦割りで算数の学習を行いました。本校の強みは、小規模校で縦割り活動が盛んなところです。異年齢の関わりは、自然なこととして子どもたちにも浸透しています。それを学習にも取り入れてみようというのが二つ目の試みです。
算数の学習は、自由進度学習で行いました。学年も違う、学習の進度も違うという環境の中で、子どもたちは自分の学びに集中しながら、時には異年齢で教え合ったり、友達と学び合ったりする姿が見られました。それぞれのペースを見守り、個性を尊重する雰囲気は、あたたかく穏やかでした。小規模校の不安としては、人間関係の固定化が挙げられます。異年齢の学習は、それを解決する一つになるのではないかと思われました。また、同時に担任の交換授業も行いました。教科担当制への挑戦です。
これも、児童と先生との関係を固定化させない工夫です。いつもとは違う先生の授業は、新鮮さがあるようで、目を輝かせて、前のめりで学習する様子が印象的でした。
三つ目は、交流給食です。異年齢で学習したときのグループで、給食を食べてみようというのが三つ目の挑戦になります。異年齢での給食は、学習の時とは違って、お互いにおしゃべりする姿が多く見られました。リラックスしている雰囲気も増し、高学年では、輪になって顔を見合わせながら食べる様子が見られました。給食は楽しくが基本であると思います。最近は、家族みんなで食事をするという家庭も少なくなってきているのではないでしょうか。誰かと一緒に食べる、みんなと一緒に楽しく食べるという時間を学校の中では体験させてあげたいと思っています。また、先生方にもゆっくりと給食を食べてほしいと思っています。教師の多くは早食いの傾向があると思います。それは、給食指導中は、味わって食べる暇がないからです。それを変えるためにはどうしたらいいのか、食缶を少なくして、配膳を少なくして準備はできないか、2クラス合同で給食が食べられないか等、色々と考え、とりあえずやってみようで試してみました。
こうした様々な挑戦ができるのは、本校職員のお陰です。本当に素敵な先生方です。校長として有り難い限りです。
学校の挑戦はこれからも続きます。それは、子どもたちだけでなく、先生方や、保護者の方々、地域の方々、みんなの幸せのためです。そして未来の社会を幸せにするためです。
どうかあたたかく見守って頂き、応援していただければと思います。
楽しい冬休みを・・・
12月24日から冬休みに入りました。
子どもたちにとっては、イベントも多く、楽しみなことが多い冬休み。
年末年始をご家族と一緒に楽しく過ごし、また元気に学校に戻ってきて欲しいと思います。
3学期は、1月7日からスタートです。
きっと、あっという間に卒業式が近づいてくることでしょう。今年は全校で卒業式を行います。
6年生の卒業をみんなでお祝いし、温かく見送りたいと思っています。
2学期の終業式。6年生には、2学期に挑戦したことを全校の前で一人ずつ発表してもらいました。
料理や勉強、ルービックキューブや図書ビンゴ、鉄棒など、様々な挑戦がありました。
どれも自分で目標を決めて達成したこと、本当に素晴らしいことだと思います。
どんなことも「まずはやってみること」が大事だと思うからです。
「失敗は何もしないことだよ。」という話を全校朝会でしたことがあります。
どんなことも自分には無理とは思わずに挑戦して欲しいと心から思っています。
学校は子どもたちの可能性を伸ばすところです。
一人一人の可能性を最大限に伸ばしたいというのが、私の、そして学校の願いです。
それぞれの挑戦が、個々の可能性を伸ばすことにつながったらいいなと思います。
また、2学期は色々な行事や学習、取組がありました。子どもたちは本当によく頑張っていました。
その頑張りは、きっと一人一人の成長の肥やしになっていると思います。
それぞれの花がきれいに咲き誇る卒業式・修了式になるように、これからも子どもたちを支えていきます。
皆様、良いお年をお迎えください。
全校遠足を終えて・・・
11月29日(金)、全校筑波山登山!!
今年で3年目を迎えた本校ならではの行事です。
当日は好天に恵まれ、紅葉も見頃、眺めも最高で、遠くには雪を被った富士山まで見えました。
たくさんの観光客の方もおり、ご迷惑をおかけしたことと思いますが、すれ違う方々に道を譲っていただいたり、励ましていただいたりしながら、何とか参加児童全員が無事に登頂することができました。
全員で登ることの意味、縦割り班で行く意味はどこにあるのか・・・
それは、やはり、学校教育目標の「自ら学び 心豊かに たくましく生きる とみせの子の育成」と、今年度の重点目標 「人間関係力を高め、挑戦し続ける子の育成と学校づくり」の達成のためです。
子どもたちは、普段から、掃除や縦割り遊びを異年齢集団のグループで行っています。このグループは、1年生から6年生までの全員を6班のグループに分けて構成し、毎年変えています。
異年齢で取り組むことの良さは、自分より年下の子と関わることで優しさや思いやりが育まれること、発達年齢に合わせた自分の役割を果たすことで自己有用感が高まること、年上の子が模範を示したり、リーダーになったりすることで自己肯定感が高まること、助け合いや励まし合いにより協力する力が身につくことなど、挙げればキリがない程たくさんあると思われます。
全校遠足は、この集大成です。
この日の子どもたちの姿、子どもたちを全力で支える先生方の姿は、本当に素晴らしく、校長として自慢に思いました。これまでの縦割り班での活動やこの全校遠足が、子どもたちをしっかりと成長させていることも実感できました。
筑波山の山頂からの景色も最高でしたが、全校で列をなして筑波山に登っていく景色も、ケーブルカーに全員が乗って紅葉を眺めながらみんなで降りる景色も、私にとっては最高で、本当に感動的でした。
感謝の気持ちでいっぱい、そして、富勢東小はやっぱり最高と叫びたい気持ちでした!(叫びましたが・・・。)
弁天マラソン大会を終えて・・・
11月19日、澄み渡る青空の下、あけぼの山農業公園内で、校内持久走大会を開催しました。
本校では、校内持久走大会を平成3年度から「弁天マラソン」と改名し、長い間続けてきています。
以前は、学校近くの公道を走っていたそうですが、子どもたちの安全を考え、令和4年度からは、あけぼの山農業公園様にご協力いただき、園内にコースを設定して行っています。大変有り難い限りです。
19日は、今年一番の冷え込みで、大変寒い中でしたが、沢山の保護者の方やご来園の一般の方々、また、地域の方に応援していただき、大いに盛り上げていただきました。
子どもたちも、沢山の温かい声援に応え、ゴールまで精一杯頑張る姿が見られました。どの子も本当によく頑張ったと思います。子どもたちの頑張る姿に大人も元気と感動を沢山もらいました。
私は、ジョギングが趣味なくらい、走ることが好きです。
小学生の頃、母校には「やまゆりマラソン」というコースがあり、毎朝全校で走る習慣がありました。
それが、学校の特色でもあり、伝統でもありました。また、日頃の練習の成果を発揮する大会が、年2回あり、その日は、終わるとお餅つきがあり、豚汁やお餅が振る舞われていたことを覚えています。
走ることが苦手だった子も、終わった後に食べるお餅や豚汁は最高だったと思います。みんなで頑張ったことを労い、大人が子ども達に「よく頑張ったね!」「凄いね!」と褒めてくれたような記憶があります。
持久走大会は、苦しい思いをする大会です。沢山の練習も必要です。苦手と思う子も多いかもしれません。この頃は、持久走大会がなくなり、記録会にしている学校も増えてきました。
本校では、この伝統ある「弁天マラソン大会」を今後どのようにしていくのか、子どもたちにとってより良いものになるようにみんなで考えていきたいと思っています。
音楽発表会を終えて
11月2日(土)本校の大きな行事である「音楽発表会」が終わりました。
この日のために、子ども達は9月から練習開始、先生方は夏休みから準備を進めてきました。
選曲には先生方の想いも込められています。勇気が出る歌、元気が出る歌、友達を思いやったり、平和への祈りが込められた歌・・・歌を通して心も成長してほしいという先生方の願いが感じられました。
子ども達は、その願いをしっかりと受け止め、感情を込めて歌っていました。一生懸命な歌声は、心にぐっと響き、技術面だけでなく内面の成長も感じた合唱でした。
また、合唱は、一人ではできません。学校という集団だからこそできるもの。当日は欠席が0でした。全校児童が揃って歌い、子ども達も私達も地域の皆さんも一緒に音楽を楽しむ、そんな素敵な時間を過ごせたことを改めて嬉しく思い、校長として幸せに感じました。
合奏は、それぞれの技術や発達段階に合わせて楽器や曲が選ばれ、練習の積み重ねが肝となりました。始めの頃と比べて、どの子もどの学年も、そしてたんぽぽ学級も、本当に上達しました。当日の合奏は、その練習の成果が発揮され見事でした。緊張の中、最後まで頑張った子ども達を心から褒めたくなりました。
本校の今年の学校経営の重点は、「人間関係力を高め、挑戦し続ける子の育成と学校づくり」です。
今回の音楽発表会を通して、私はそれをみんなで達成できたのではないかと思えました。
本校の教職員と子ども達を誇りに思います。そしてまた、私達を支えてくださった保護者の皆様や地域の皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。
1・2年生の校外学習
10月18日(金)、1・2年生と一緒に船橋・アンデルセン公園へ行ってきました。
朝はどしゃぶりの雨で天気がとっても心配でしたが、集合した時から子どもたちはニコニコ笑顔。
楽しみにしていた気持ちが伝わってきました。子どもたちの気持ちが天に届いたのでしょうか?
その後は、朝ほどの大雨にはならず、色々な活動を楽しむことができました。アスレチックがあまりできなかったことが、少し残念でしたが、みんなお弁当やおやつタイムを大いに楽しんでいました。
校外学習では、1・2年生といえども、ぞれぞれ役割があります。
まずは、実行委員のメンバー。バスの中での出発の会、到着の会は素晴らしかったです。しっかりとした司会や挨拶、落ち着いた口調に練習の成果が出ていました。本当に素敵でした!!
続いて、バスレク係。みんなが楽しめるようにと、練りに練った内容と進行、とても感心しました。お陰で到着するまでみんなの笑い声や歌声が響き、酔う子も一人もいませんでした。先生方の指導もさすがでした。
班行動は、今回は雨のため、出番が少なかったかも知れませんが、それぞれが役割を意識しながら、班ごとに並んだり、声を掛け合ったりする姿が見られました。外に出ると、普段の様子が顕著に表れますが、どの子もしっかりと園の方や先生方の話を聞いて、楽しく制作活動をしたり、遊んだりしていました。
みんなよく頑張り、成長が見られ、楽しい校外学習でした。
保護者の皆様には、朝早い出発となりましたが、お弁当作りをはじめ、ご協力いただきありがとうございました。次は全校筑波山登山です。(雨天の場合は国立科学博物館)
今回の経験を生かして、みんなで協力して、さらに充実した校外学習にしたいと思います。
修学旅行へ行ってきました!
9月12日(木)、13日(金)6年生と一緒に修学旅行へ行ってきました。6年生は18人。欠席もなく、全員参加することができ何よりでした。集合時間がかなり早かったにもかかわらず、全員時間通りに集合し、予定通り出発できました。さすが、6年生です。保護者の皆様にも感謝申し上げます。
お陰様で国会議事堂へ時間通りに到着し、最高裁判所も含め余裕を持って見学することができました。
国会議事堂と最高裁判所は、6年生の社会科で学習しますが、本物を見る機会は大変貴重です。建物の重厚感や広さ、崇高感といったものは、その場所でしか味わえません。どちらも、子ども達は真剣に見学し、積極的に質問もし、見聞を広めていました。バスレクの中での予習クイズもとても役に立ったようです。見学の態度も大変立派でした。自慢の6年生です。
1日目は、浅草の仲見世通りにも行きました。ここは班行動でしたが、みんな仲良く観光を楽しむ様子が見られ、何とも微笑ましかったです。いちご飴を食べたり、最中を食べたり、おそろいのお土産を選んだり・・・旅の思い出が広がったようです。班ごとにスカイツリーをまねて撮った写真も最高でした!
旅館は、成田山新勝寺の老舗旅館、若松旅館に宿泊させていただきました。何とも贅沢な旅行です。
翌朝には、新勝寺で修行を体験。みんな正座もよく頑張っていました。きっと御利益があるでしょうね。
2日目は、佐原と佐倉で歴史の学習。佐原では伊能忠敬記念館を、佐倉では国立歴史民俗博物館を見学しました。どちらもフリーでしたが、各自が興味を持った物をじっくりと見学する姿が見られ、学習の深まりや意欲を感じました。「自ら学ぶ姿」本校の学校教育目標に叶っています。
二日間を通して感じた事は、6年生の素晴らしさです。特に18人の仲の良さには感動しました。
仲良きことは素晴らしきかな・・・と。
旅行はどこへ行くか、何をするかも重要ですが、誰と行くかは、一番大きな問題ではないかと思います。一緒に過ごす時間も長く、宿泊もするとなると、どうでしょう。人間関係がギスギスした中では、普段より苦痛が増えてしまう可能性もあります。でも、子ども達はこの二日間、ずっと楽しそうで、笑顔が沢山見られ、もめることも悲しむこともなく、お互いにとっていい時間、温かい時間を過ごしていたように感じました。
それが私はとても嬉しく、誇らしく、また羨ましくも思いました。
また、この姿こそが、本校の目指す姿ではないかと感じました。
本校のめざす児童像は、「やさしく、かしこく、たくましく」です。
学校教育目標は、「自ら学び 心豊かにたくましく生きる とみせの子の育成」です。
もちろん、目標を高く掲げれば、まだまだ成長する余地はあります。ただ、子ども達は十分にそこに近づいていると感じましたし、どの子もその子なりに社会性や協調性がよく育っていると思いました。
素晴らしい修学旅行だったと思います。この経験をこれからの人生に生かしていってほしいです。
最高の思い出をつくってくれた6年生と保護者の皆様、関係者の皆様に心から感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
【お知らせ】
「いじめ防止基本方針」のメニュー内に「学校生活について」「富勢東小よい子の一日」も公開しています。
※このホームページに掲載している文章・画像・楽曲の著作権は柏市立富勢東小学校とその情報提供者に属します。無断での転載・複製・配布は一切お断りいたします。