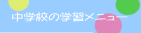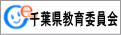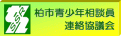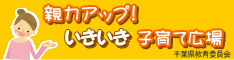文字
背景
行間
い じ め 防 止 基 本 方 針
柏市立酒井根中学校 いじめ防止基本方針
上記のリンクより、ご覧ください。
お知らせ
【sigfyについて】
療養報告書
学習サイト
新着情報
学校情報
〒277-0053
千葉県柏市酒井根1-3-1
TEL:04-7174-8520
FAX:04-7174-5492